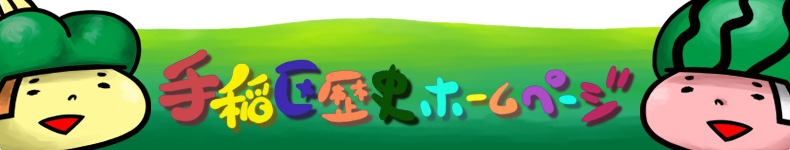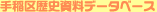
|
<資料名> |
縄綯機「製縄機」 |
|
<よみがな> |
なわないき「せいなわき」 |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
55 |
| <大きさ(横)> |
105 |
| <大きさ(高さ)> |
75 |
| <大きさ(直径)> |
42 |
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
稲わらの縄は昔はお百姓が夜なべ仕事に両手のひらでなって作っていた
が、大変な苦労であったと推測される。
この機械が大正時代(19
12年頃〜)から出始めて、仕事もずいぶん楽になり、作業量も増えた。
これは人力用足踏式縄綯機である。両足を交互に踏むと、歯車の作
用によりラッパ管でわらに下よりが懸かり、同時に上よりが懸かって縄と
なり、巻取胴に巻き取られるのである。 |
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
07:産業 |
| <中分類(コード)> |
05:工業(土木・建設) |
| <小分類(コード)> |
04:わら・竹細工製作用具: |
| <個別番号(コード)> |
11-0176 |
|