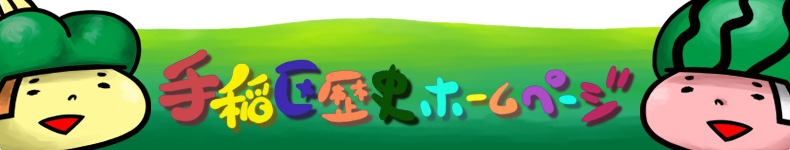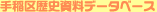
|
<資料名> |
馬鍬(まんが) |
|
<よみがな> |
まぐわ(まんが) |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
|
| <大きさ(横)> |
|
| <大きさ(高さ)> |
|
| <大きさ(直径)> |
|
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
田に水をはり土を柔らかくしたあと、これを使って土を砕きながらかき
まぜたので「代掻」ともいっていたのである。鎖に引き綱をつけて馬に引
かせ、横棒を人力で操りながら作業をしたのである。
馬鍬は、わが
国に古くからあり、主に代掻に用いられていた。しかし、畑地でも、砕土
・土ならしに利用されていたのであるが、明治(1868年〜)時代の初
め、プラウ(起耕農具)などと共に輸入されたハロー(洋式砕土・土なら
し農具)により、畑地砕土、土ならしには使われなくなった。
「ま
んが」とも言われたが、馬鍬の方言である。 |
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
07:産業 |
| <中分類(コード)> |
01:農業 |
| <小分類(コード)> |
01:耕運用具<土おこしの用具>: |
| <個別番号(コード)> |
11-0167 |
|