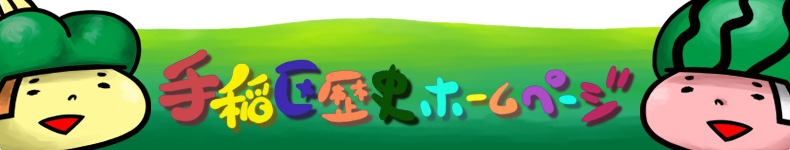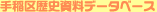
|
<資料名> |
むしろ編み器 |
|
<よみがな> |
むしろあみき |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
|
| <大きさ(横)> |
|
| <大きさ(高さ)> |
|
| <大きさ(直径)> |
|
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
稲わらを原料とし、それを編んで敷物や荷物の包装にする「むしろ」を
自分たちの手で作っていた。
これはその編み器の部分品(おさ、ひ
ご)で江戸時代後期(1860年ころ)から大正時代中期(1920年こ
ろ)使用していたものである。
使い方は、おさの穴の開いていると
ころに縦縄を通し、上下にしっかりと張って止める。竹(ひご)でわらを
縦縄の間を交互に前後して編んでいく。通したあと、あさを上下して織っ
た。
作業は腰をかけて、手作業で行った。
おさ
幅 7.0cm
長さ 96.5cm
竹
幅 1.8cm
長さ 120.0cm |
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
07:産業 |
| <中分類(コード)> |
05:工業(土木・建設) |
| <小分類(コード)> |
04:わら・竹細工製作用具: |
| <個別番号(コード)> |
11-0164 |
|