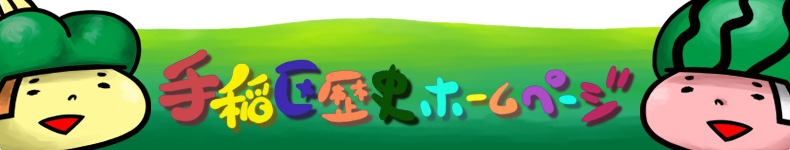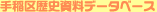
|
<資料名> |
竿秤 |
|
<よみがな> |
さおばかり |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
|
| <大きさ(横)> |
|
| <大きさ(高さ)> |
|
| <大きさ(直径)> |
|
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
古く昔から、尺貫法が廃止されメートル法が実施される昭和33年(1
958年)までの間、農家の俵物、生産物の重量測定に使用された。この
竿秤は、21貫匁(78.75kg)まで計ることができる秤である。そ
のため、当時米俵が16貫(60.0kg)、えん麦12貫(45.0k
g)であったので、この棒秤は農家用として十分活用された。使い方は皮
でできている把手を支点として量るべき俵等を端のカギに吊るし、竿の他
の端に分銅をかけ、竿が水平になるまでその分胴を左右に移動させ竿の目
盛りによってその物の重さを量るものである。
柄(縦)
126.0cm
分銅直径 9.0cm
分銅高さ
14.0cm |
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
07:産業 |
| <中分類(コード)> |
07:商業 |
| <小分類(コード)> |
03:計算・計量用具<はかり、そろばんなど>: |
| <個別番号(コード)> |
11-0141 |
|