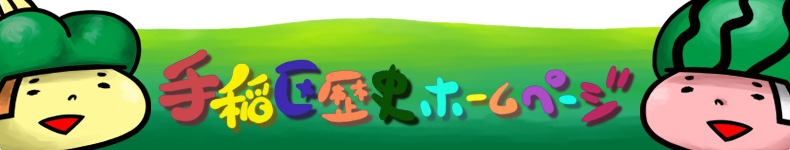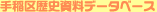
|
<資料名> |
一斗枡 |
|
<よみがな> |
いっとます |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
|
| <大きさ(横)> |
|
| <大きさ(高さ)> |
|
| <大きさ(直径)> |
|
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
枡は、古く江戸時代(1600年代)から尺貫法が廃止される昭和33
年(1958年)まで使用されたもので、液体、粉状の物、粒状の物など
の分量を計る器である。正方形、円筒形のものがあり、粉・粒状の物をは
かる公定枡の器の縁には誤りや不正を防ぐため鉄わくがついている。
この一升枡(18.039リットル)は、粒状の物(米、麦、豆類)を
計るために使ったもので、明治36年(1903年)に役所が検定し正し
いことが認められて検定証印がつけられた枡である。
使い方は、枡
の中に粒状の穀物をいっぱい入れ、丸い棒(斗棒)で器の縁と水平になる
ようかきとって計るものである。他に一升枡(1.8037リットル)と
その半分の五合枡がある。
縦 35.5cm
横
35.5cm
高さ 25.0cm
斗棒
縦
39.5cm
横 6.0 cm |
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
07:産業 |
| <中分類(コード)> |
07:商業 |
| <小分類(コード)> |
03:計算・計量用具<はかり、そろばんなど>: |
| <個別番号(コード)> |
11-0140 |
|