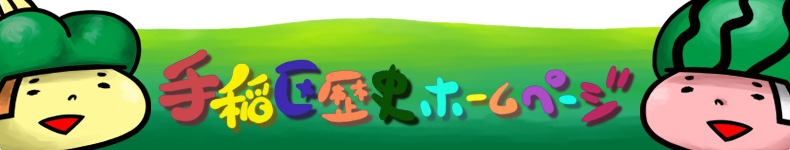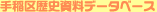
|
<資料名> |
粟ふるい |
|
<よみがな> |
あわふるい |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
|
| <大きさ(横)> |
|
| <大きさ(高さ)> |
|
| <大きさ(直径)> |
|
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
「ふるい」は、とうし、もみとうしともいう。脱穀後の籾とわらのふる
い分けをしたり、穀物(あわ、ひえ、豆類)の選別に利用された。
このふるいは、大正時代(〜1920年)まで使っていた粟を振るい落と
す専用のふるいで、網目を通して粟が落ち、ふるいの中に雑物が残るよう
になっている。網目は金網になっているが、竹や糸を使用しているものも
ある。また、網目の大きさを変えることによって用途が変わってくる。
網目 0.3cm
直径(横) 36.5cm
深さ(高さ) 11.7cm |
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
07:産業 |
| <中分類(コード)> |
01:農業 |
| <小分類(コード)> |
05:脱穀用具<もみがらを取る用具>: |
| <個別番号(コード)> |
11-0138 |
|