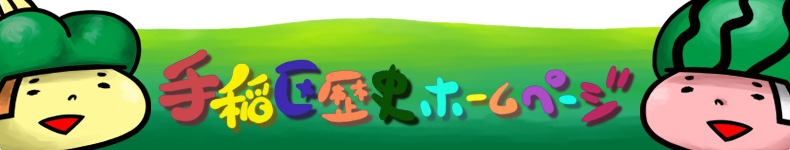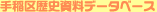
|
<資料名> |
唐箕 |
|
<よみがな> |
からみ |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
173 |
| <大きさ(横)> |
46 |
| <大きさ(高さ)> |
114 |
| <大きさ(直径)> |
|
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
開拓当時から使われていた穀類の選別農具である。
この唐箕は、
明治20年(1887年)製作されたもので、把手(ハンドル)の部分が
歯車形式に改造されている。太鼓型の胴についてい把手(ハンドル)を回
転させ、胴の中の4枚の羽根を回して風を起こす。
上部の漏斗から
穀物を落とすと、風によって重い充実した穀粒は手前の第1口に落ち、軽
い穀粒は第2口へ分離される。また、わら屑やチリは前の口より吹き飛ば
されて出てくる。玄米中の屑米の除去にも使用された。 |
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
07:産業 |
| <中分類(コード)> |
01:農業 |
| <小分類(コード)> |
05:脱穀用具<もみがらを取る用具>: |
| <個別番号(コード)> |
11-0137 |
|