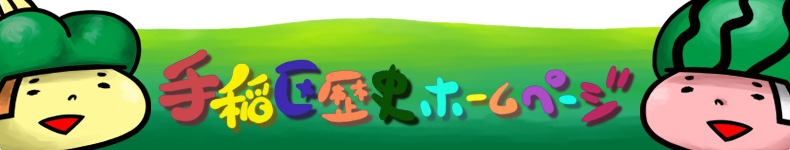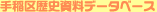
|
<資料名> |
蚕座 |
|
<よみがな> |
さんざ |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
|
| <大きさ(横)> |
|
| <大きさ(高さ)> |
|
| <大きさ(直径)> |
|
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
北海道開拓の初めころ、開拓使は蚕(かいこ)を飼うことをすすめた。
手稲でも明治6年から明治14年ころ(1873〜1887年)まで、養
蚕を営んで、まゆの生産をしていた。この蚕座はその頃使われていたもの
である。
卵からかえった、蚕の幼虫である毛子(けご)をこの上に
移して、桑の葉をきざみ、十分に与えて成長させるのである。蚕はやがて
口から細い糸を吐き出し、自分の体を包みこんでまゆを作り、その中でさ
なぎになる。そのまゆから絹糸を取るのである。
蚕座は笹竹を割っ
て薄くし、亀甲形(きっこうがた)に編み、ふちも笹竹で作られている。
蚕座はいくつも台の上に並べられたり、また何段かのすかし棚に納められ
ていた。 |
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
07:産業 |
| <中分類(コード)> |
05:工業(土木・建設) |
| <小分類(コード)> |
02:繊維・皮革工業用具<せんい・かわ工業用具>: |
| <個別番号(コード)> |
11-0132 |
|