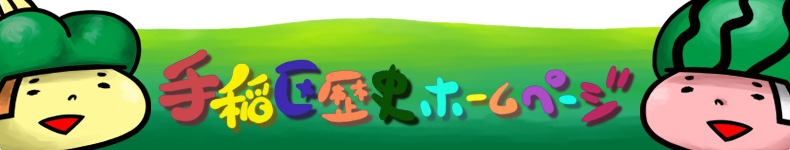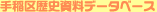
|
<資料名> |
鳶口 |
|
<よみがな> |
とびくち |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
|
| <大きさ(横)> |
|
| <大きさ(高さ)> |
|
| <大きさ(直径)> |
|
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
棒の先端に鳶の口さきに似た鉄製の鉤(かぎ)を付けていることから鳶
口と呼ばれるようになった。
この鳶口は、造材山で材木(丸太など
)を引っかけて移動するなどの操作に用いられた道具で、昭和30年(1
955年)代まで使われていた。
柄の頑丈さと鳶口の部分の反り上
がった構造は、梃子(テコ)の原理を巧みに工夫して強く働かせるために
考えられたものである。 |
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
07:産業 |
| <中分類(コード)> |
02:林業 |
| <小分類(コード)> |
04:: |
| <個別番号(コード)> |
11-0124 |
|