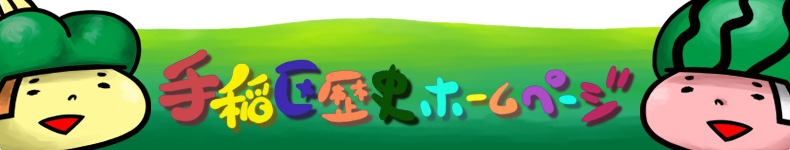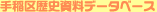
|
<資料名> |
挽碓 |
|
<よみがな> |
ひきうす |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
|
| <大きさ(横)> |
|
| <大きさ(高さ)> |
|
| <大きさ(直径)> |
|
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
挽碓のことを麿臼(すりうす)とか石臼(いしうす)といい、明治・大
正・昭和時代には一般家庭で盛んに、麦、ソバ、大豆を製粉するのに使わ
れていたものである。昭和に入って、動力脱穀機や製粉機が普及するにつ
れて使用されなくなったのである。
これは、あまり古いものではな
いが、開拓者の生活がしのばれる重要な資料である。
柄の長さ
23.3cm
直径 28.5cm
高さ 26
.5cm
|
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
06:生活 |
| <中分類(コード)> |
02:食習<食べ物に関するもの> |
| <小分類(コード)> |
06:保存・加工用具<うすなど>: |
| <個別番号(コード)> |
11-0108 |
|