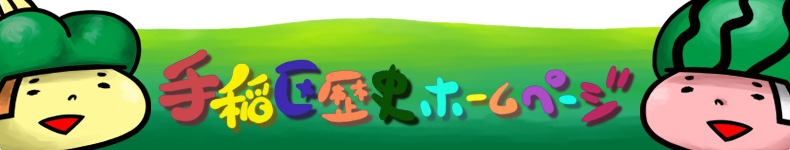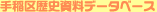
|
<資料名> |
ランプ |
|
<よみがな> |
らんぷ |
| <写真> |
|
| <収集地> |
|
|
<受入区分> |
|
| <製作地> |
|
| <製作年代> |
|
| <使用地> |
|
| <使用年代> |
|
| <大きさ(縦)> |
|
| <大きさ(横)> |
|
| <大きさ(高さ)> |
|
| <大きさ(直径)> |
|
| <材質・材料> |
|
| <備考・コメント> |
石油を使う照明器具。油壷(あぶらつぼ)、灯心(とうしん)、ホヤ(
ガラス製の下の部分がふくらんだ円筒状のもの)、笠(かさ)の4つの部
分からできている。
家庭用は主として真の先が平らな平心を使い、
二分芯(0.7cmくらい)、三分芯、五分芯などがあった。
ここ
手稲村の全村電化(村のすべての家に電気が通じること)は昭和22年(
1947)で、それまで長い間、各地域では石油ランプが使われていた。
このランプにはホヤ(風よけや防火、危険防止のためのもの)がつ
いていないが、ランプ点火前のホヤ掃除(布で筒の中のすすをふきとる)
は手の小さな子供に都合がよく、子供たちの大事な仕事の一つだった。
※ 笠の直径 約29.0cm、高さ 約40.0cm、油壺長径
約11.0cm
ホヤの部分なし。
他に同
様のランプあり。 |
| <収蔵施設コード> |
11:手稲記念館 |
| <大分類(コード)> |
06:生活 |
| <中分類(コード)> |
03:居住<すまいに関するもの> |
| <小分類(コード)> |
03:照明具<ランプなど>: |
| <個別番号(コード)> |
11-0055 |
|